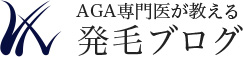この記事で説明する内容は?
人間の髪の毛はずっと伸び続けているのではありません。
一定の期間成長した後、自然に抜け、しばらくすると新しい毛髪が生えてきます。
このサイクルが乱れると、毛髪が十分に成長しないまま未熟な状態で脱毛し、薄毛になるのです。
AGAは、このサイクルが長期にわたって正常に保たれていないために起こります。
サイクルを乱す原因に合わせた必要な対策を行えば、進行性のAGAになることなく薄毛を解消できるでしょう。
とにかく早め早めの対応が薄毛に打ち勝つベストの対策方法です。

総合頭髪治療を専門とする大阪AGA加藤クリニックグループ総院長 加藤です
臨床的に効果が認められた様々な薄毛・脱毛に有効な最先端の治療を得意としています
平成13年 近畿大学医学部 卒業
平成13年 大阪医科大学医学部付属病院 形成外科入局 麻酔科勤務
平成17年 大手美容外科 形成外科部長 植毛部門勤務
平成23年 大阪AGA加藤クリニック開業
日本形成外科学会 正会員
日本再生医療学会 正会員
国際抗老化再生医療学会 正会員
毛周期(ヘアサイクル)とは?

毛周期(ヘアサイクル)とは、髪が生えて抜け落ち、再び生えてくる周期のことです。
1本1本の髪には寿命があり、ある程度成長し続けた髪は自然と抜け落ちます。
脱毛後、再び新しい髪が成長し、伸び続けたのちに再び脱毛する一連の流れがヘアサイクル(毛周期)です。
通常のヘアサイクルは、男性が3~5年、女性が4~6年で1周します。
ヘアサイクルの主なステージについて説明します。
成長期
成長期とは、髪が成長する段階のことです。
髪は1日0.3~0.4mm成長し、1年で約15cm伸びます。
髪の毛は、毛根にある毛母細胞が分裂し、増殖することで増えていきます。
細胞分裂が活発に行われて作られた毛は、その後上部へと押し上げられます。
ですから、毛根が残っているかぎり毛母細胞の分裂・増殖も行われます。
正常な毛球の場合、2年~6年程度成長期が持続します。
通常は、頭髪全体の85~90%が成長期にいるとされています。
成長期が長ければ長いほど、髪は太く長く成長できます。
抜け毛1本1本が細く短い場合は、ヘアサイクルが乱れている可能性が考えられます。
退行期
退行期は、毛根の働きが弱くなる段階です。
毛母細胞の分裂して髪の毛が増えるには、毛乳頭細胞と言われる細胞からの指令や栄養の供給が欠かせません。
この毛乳頭細胞の働きが低下すると、毛根の働きが弱くなり髪の成長スピードが遅くなってきます。
毛乳頭細胞が毛母細胞から離れ、髪の根元の毛球部は委縮して徐々に小さくなります。
退行期は2~3週間で、対抗機にある髪は全体の約1%を占めます。
退行期の毛髪は、ブラッシングやシャンプーなどで抜けやすいのが特徴です。
休止期
休止期は、髪の成長が完全に止まった状態です。
毛乳頭細胞が縮小して指令や栄養の供給が止まります。
休止期は2~3ヶ月続き、休止期の髪が占める割合は全体の10~20%です。
毛根は休止期の間に新しい毛髪をつくる準備をはじめていて、再び成長期のサイクルへと移行していきます。
成長期に戻る
やがて、次のサイクルの発生期へと進み、毛乳頭細胞が活動を再開します。
造られた新しい毛が古い毛を押し出すように生えてきて、古い毛が自然に抜けます。
髪が抜けるのはサイクルの一部で自然現象です。
1日に抜ける毛髪の本数は、50~150本程度です。
サイクルを周回するからこそ、常に新しい毛髪に生まれ変わってくれるのです。
ヘアサイクルの乱れとは?
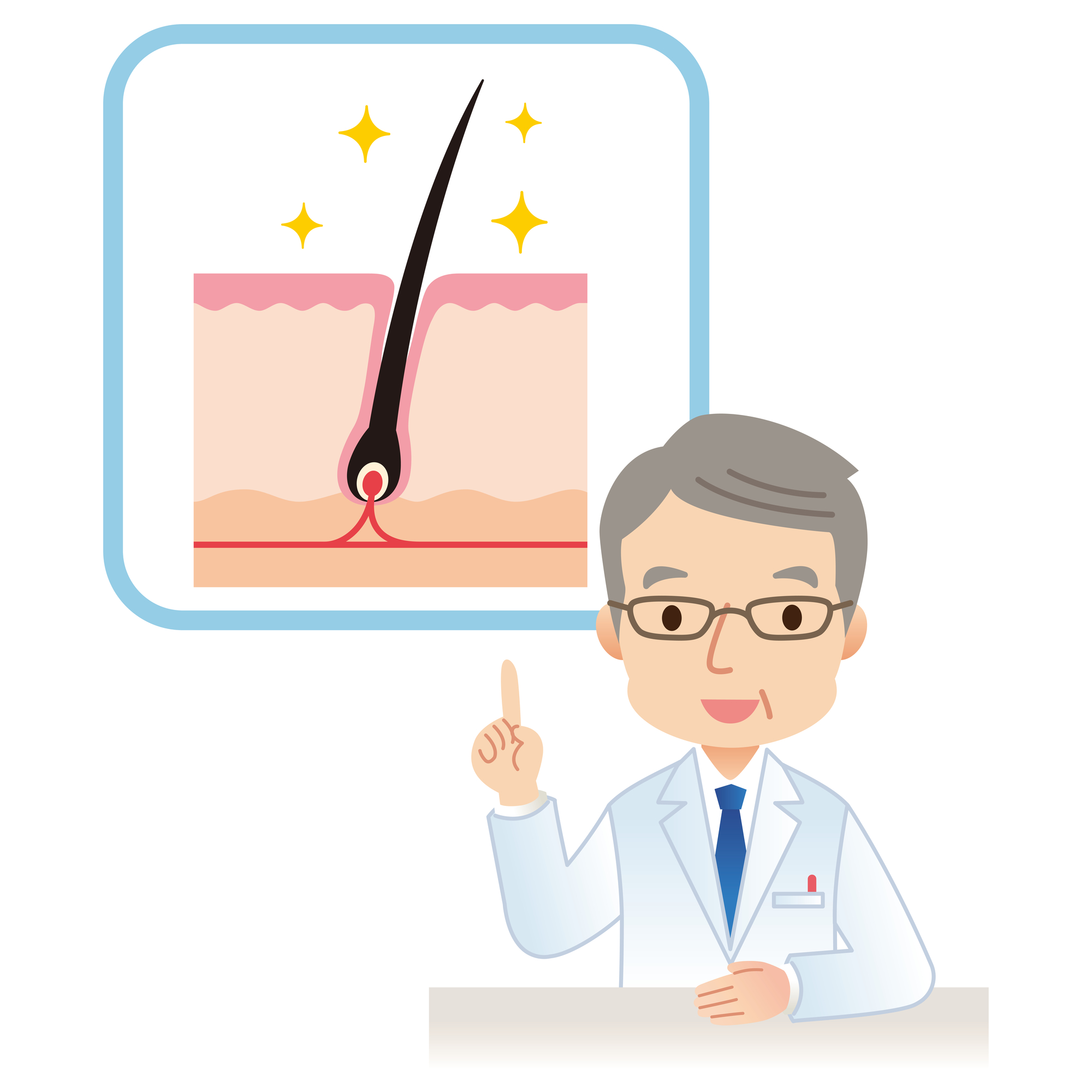
ヘアサイクルの乱れとは、ヘアサイクルの成長期が短くなってしまった状態です。
髪がどんどん伸びるのは成長期だけなので、成長期が短いと髪が十分に育ちません。
生育不足の髪の毛は、短く細いまま退行期に入ってしまう、またはその前に抜けてしまいます。
サイクルが正常でも髪は1日に50~100本抜けますので、自然に抜けたものについては心配いりません。
しかし、ヘアサイクルが乱れると1日に抜ける毛髪の本数は200本以上になります。
明らかに抜け毛が増えたと感じた場合は、頭皮や髪に何らかの問題が起きている可能性があります。
ヘアサイクルが乱れた部分は地肌が透けて見えるようになり、いわゆる薄毛になります。
AGAとヘアサイクルの乱れの関係は?
AGA(男性型脱毛症)は、男性ホルモンの異常によって毛母細胞が攻撃されて毛髪の成長サイクルが長期にわたって乱れてしまうのが主な原因です。
残念ながら、ヘアサイクルの乱れ自体が男性ホルモンの異常によって引き起こされ、AGAへつながっています。
AGAは発症すると、放っておく限りどこまでも進行し続けます。
自然治癒は望めないのが現実です。
成長期を伸ばして正常なサイクルに近づけるために、薬剤などによって男性ホルモンをコントロールする必要があります。
薬は1回きりではなく、継続的に飲むことでAGAの進行抑制が期待できるため根気よく治療を続けましょう。
ヘアサイクルの乱れを引き起こすAGA以外の4つの原因
AGA以外にヘアサイクルが乱れる主な原因は以下です。
- 生活習慣
- ストレス
- 季節的要因
- 加齢
上記の原因はお互いに影響し合ってAGAの発症やヘアサイクルの乱れを加速させることも考えられます。
それぞれの原因とヘアサイクルの関係を詳しく解説していきます。
生活習慣
睡眠不足や喫煙、過度の飲酒、栄養不足の食事などの生活習慣の乱れは、毛周期が乱れる原因です。
睡眠不足は、髪の生成に必要な成長ホルモンの分泌を阻害します。
また、睡眠不足や喫煙によるニコチン摂取は頭皮の血管収縮にもつながります。
血行不良が生じることで、毛根を太らせるために十分な栄養が行き渡らなくなります。
さらに過度な飲酒は、髪の生成に必要な亜鉛を消費することで栄養不足を招くのです。
バランスを欠いた食事が続くと、髪の生成に必要な以下のような成分を摂取できなくなります。
- タンパク質
髪の主成分です - ビタミンB2・B6
代謝に関わる - ビタミンE
血行を促進する - 亜鉛
髪の主成分ケラチンの合成をサポート
さまざまな栄養をバランスよくとることで、髪を生成する準備が整うのです。
ストレス
ストレスを受けると、自律神経のうち交感神経が常に優位になり、バランスが乱れて血行不良が生じます。
交感神経が優位になると血管は収縮し、毛乳頭細胞への栄養の供給が低下するのです。
結果的にヘアサイクルの乱れを引き起こし、薄毛を悪化させてしまうのです。
ストレスは睡眠不足にもつながりやすく、毛根のためにますますよくない環境をつくります。
季節的要因
「秋口に抜け毛が増える」と実感している人も多いようです。
ヘアサイクルは季節でも乱れる傾向もあります。
休止期にある髪の毛が全体に占める割合は季節が要因で変化します。
休止期の毛の量がピークとなるのは夏初めの7月だといわれます。
休止期は約3カ月続きますので、9~10月までは自然脱毛が増加するのです。
加齢
ヘアサイクルは加齢によっても変化します。
ただし、早い女性では40代で迎える閉経は女性のAGA=FAGA(女性男性型脱毛症)と密接な関係を持っていると考えられています。
ヘアサイクルの成長期が短縮してしまうFAGAについては、薬の服用によって薄毛が解消する場合もあります。
早めに専門の医療機関へ相談しましょう。
ヘアサイクルを正常化させる方法
薄毛を予防・改善するためにヘアサイクルを正常化させる主な方法は以下です。
- AGA治療
- 生活習慣の改善
- ストレス解消
それぞれの方法を解説していきます。
AGA治療を始めたのに効果が出ず、AGA治療を止めたいと思う原因を以下の記事で解説しています。
AGA治療
ヘアサイクルの乱れを改善するもっとも効果的な方法は専門医によるAGA治療です。
薄毛専門クリニックでのAGA治療では、主に内服薬や外用薬による投薬治療を行います。
AGA頭髪治療専門クリニックでは、患者さんの体の負担が少ない治療法から試していきます。
血液検査や、カウンセリングなどの結果を考慮したうえで、医師がお薬を処方します。
「AGA対応可能」と謳う一般の皮膚科・美容皮膚科とAGA専門クリニックの違い、症状による使い分け方法については以下の記事で詳しく説明しています。
1種類だけの「単剤処方」で結果が出なければ、2種類のお薬を処方する「多剤処方」に変更していきます。
多剤処方でも結果が出ない場合にはAGAメソセラピー、オーダーメイド処方などの他の治療プランに変更します。
ヘアサイクルが乱れる原因物質に直接はたらきかけるので、効率よく確実に効果を実感できます。
AGA専門クリニックの費用、通院回数・期間についてはこちらの記事で詳しく説明しています。
生活習慣の改善
ヘアサイクルが乱れる原因が生活習慣にあるならば、睡眠時間や食事内容、喫煙の習慣を見直しましょう。
健康的な毛髪を保つにはタンパク質・ビタミン・ミネラルの三大栄養素をバランス良く摂取することが重要です。
特に重要な栄養素が髪の毛の材料となる「ケラチン」というタンパク質です。
ケラチンはシスチンという準必須アミノ酸を多く含んでいます。
シスチンを効率的に取り込むには卵や鶏肉を積極的に摂取するとよいでしょう。
また、ミネラルの一種である亜鉛はケラチンの合成をサポートする役割があります。
牡蠣やレバーなどの亜鉛を含んでいる食材も摂取するとよいでしょう。
睡眠時間は1日8時間眠ることが健康に良いと認識している人が多いようですが、年齢に適した睡眠時間を確保できれば問題ありません。
以下に年齢別の適切な睡眠時間を示します。
- 幼児から10歳まで 8~9時間
- 10歳から15歳まで 8時間前後
- 20歳から25歳まで 7時間前後
- 40代 6時間30分
- 60代 6時間
不規則な生活を送っている自覚がある方は、睡眠・食事・喫煙習慣を見直してヘアサイクルの正常化を目指していきましょう。
ストレス解消
ストレスを上手に発散してヘアサイクルを正常化させましょう。
ストレス発散をする前に、ストレスの原因を突き止める必要があります。
さらに、自分が一番リラックスできる方法を考えてみましょう。
趣味に没頭するのもいいですし、スポーツで気分がすっきりすることもあります。
あまり気張ることなく自分に合ったストレス解消法を探してみてください。
また悩みを相談する相手も重要になります。
親しい友人や、実績の厚い薄毛専門クリニックのカウンセラーに相談することをおすすめします。
まとめ・ヘアサイクルの乱れは薄毛専門医へご相談ください
ストレスや食生活の乱れなどの一時的な要因でヘアサイクルの乱れが生じる方もいますし、AGAによってヘアサイクルが乱れる方もおられます。
様々な要因がお互いに影響し合って、AGAの発症やヘアサイクルの乱れを加速させることも多いようです。
AGAは進行性の病気なのでセルフケアで改善はできません。
放っておくと髪の成長期は短いままで、薄毛もどんどん悪化します。
ためらうことなく薄毛専門クリニックの専門医に早めにお問い合わせください。